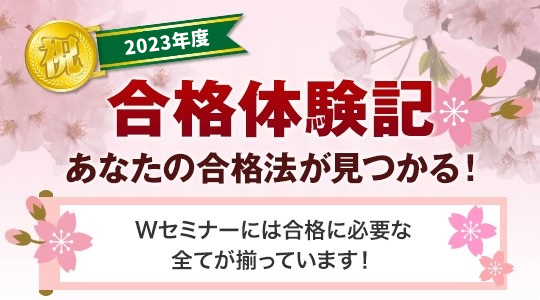司法書士
不動産登記や商業登記などの登記業務のスペシャリストでありながら、成年後見制度や簡易裁判所における訴訟代理などに関わることができる「頼れる身近な法律家」
思い立ったら学習開始!開講時期や学習レベルに合わせて
最適な司法書士試験対策コースが選択できます!
-
初学者の方
はじめて試験を受けられる方
-
受験経験者の方
試験を受験した経験がある方
-
直前対策・模試
年明けからの直前対策
-
合格者の方
認定考査対策講座
開講コース一覧
入門総合本科生(2026年合格目標)
| 早割他資格割U30割引
2024年5月~開講 |
最長期間で学習でき、確実性を最重視する方にオススメの総合コース! ★早割キャンペーン実施中!【5/31(金)まで】 |
|---|
山本オートマチック(2025年合格目標)
| 早割・特別再受講割引給付制度
2024年4月~開講 |
短期合格コースの決定版! ★早割キャンペーン実施中!【5/31(金)まで】 |
|---|
入門総合本科生(2025年合格目標)
| 早割・特別再受講割引
2024年3月~開講 |
3段階学習で確実性の高い総合コース! ★早割キャンペーン実施中!【5/31(金)まで】 |
|---|
パック(2024年合格目標)
|
2024年3・4月~開講 |
直前期の総仕上げに最適!ズバリ的中・論点的中続出の予想問題をギュッと詰め込んだ内容で本試験レベルの実践力を磨き上げる! 【受講料例】 Web通信講座(解説講義あり) ¥104,500 |
|---|
|
2024年1月~開講 |
コンパクトなカリキュラムでありながらインプットとアウトプットトレーニングの両立を実現! ・択一式対策講座【実践編】(33回) |
|---|
|
2024年1月~開講 |
年始から全科目で本試験出題可能性が高い論点を”全潰し“し、 直前期は本試験レベルの問題で“合格力完成”へ昇りつめる! ・科目別全潰し答練(12回) |
|---|
|
2023年11月~開講 |
上級総合本科生等の方が答練を追加したい場合に最適! ・総合力底上げ答練(6回) |
|---|
単科生・オプション講座(2024年合格目標)
|
様々なアプローチで【択一式】を基礎から応用まで徹底的に学習!
・択一式対策講座【理論編】 (2023年8月~開講) |
|
様々なアプローチで【記述式】を基礎から応用まで徹底的に学習!
・<山本>オートマチックシステム記述式講座 (2023年9月~開講) |
|
基礎から本試験レベルまで時期に応じた問題演習で実戦力を強化! ・総合力底上げ答練 (2023年11月~開講) |
本科生(2024年合格目標)
|
給付制度
2023年11月~2024年1月開講 |
【択一式が基準点付近の方向けの本科生】 ・記述式対策講座(26回) |
|---|
|
給付制度
2023年8月~11月開講 |
合格に必要なすべてを提供する総合コース! ・択一式対策講座【理論編】(66回) |
|---|
|
2023年8月~11月開講 |
<山本オートマチック>中上級者向けの総合コース! ・山本プレミアム中上級講座(58回) |
|---|
|
給付制度
2023年11月~開講 |
時期に応じて答練に求められる全てを提供!法改正対策講座で改正点の知識整理もできる! ・総合力底上げ答練(6回) |
|---|
|
2023年11月~開講 |
答練を中心に学習を進めたい!記述式対策を完璧にしたい!その両方を一気に実現できる! ・総合力底上げ答練(6回) |
|---|
答練パック(2024年合格目標)
|
2024年3・4月~開講 |
直前期の総仕上げに最適!ズバリ的中・論点的中続出の予想問題をギュッと詰め込んだ内容で本試験レベルの実践力を磨き上げる! 【受講料例】 Web通信講座(解説講義あり) ¥104,500 |
|---|
直前対策コース(2024年合格目標)
|
予想論点セット 2024年4月~開講 全13回 |
本試験で出題可能性の高い論点を直前期に総整理! 【受講料例】 Web通信講座(解説講義あり) ¥61,600 |
|---|
|
2024年2月~開講 全10回 |
知識があっても点が取れなければ意味がない!過去問を題材に「解法テクニック」を伝授! 【受講料例】 Web通信講座 ¥51,700 |
|---|
|
2024年2月~開講 全2回 |
法改正(2024年司法書士試験で新たに出題範囲に加わるもの)をコンパクトに押さえる! 【受講料例】 Web通信講座 ¥11,000 |
|---|
|
2024年2月~開講 33年分(33回分)×約45分 →不動産登記法15年分(15問分) →商業登記法18年分(18問分) |
姫野講師の解法をフルサイズ記述式過去問で実践! 【受講料例】 Web通信講座 ¥70,400 ◆当オプション講座のお申込みについて |
|---|
|
2024年3月~開講 全3回 |
本試験形式の記述式予想問題を徹底演習!即効性かつ汎用性の高い解法を習得! 【受講料例】 Web通信講座 ¥9,900 |
|---|
|
2024年2月~開講 択一式午後35問 2回/解説講義2回(各回3時間) |
午後の部は時間との勝負!択一式を1時間以内で解き切るためのノウハウがここに! 【受講料例】 Web通信講座 ¥7,700 |
|---|
|
2024年2月~開講 全1回 |
毎年的中多数の「本試験予想論点集」を用いた解説講座! 【受講料例】 Web通信講座(テキスト有り) ¥7,700 |
|---|
|
2024年2月~開講 各コース1冊 |
人気の受講生限定レジュメを自主リメイクして一般販売!オートマテキスト学習者の学習効率向上に役立ちます! 【受講料例】 資料通信講座 ¥2,200 |
|---|
|
2024年2月~開講 全2回 |
民訴等を6時間でまるっと総ざらい!短時間で総復習ができる便利講座! 【受講料例】 Web通信講座(テキスト有り) ¥9,900 |
|---|
答練コース(2024年合格目標)
|
2024年3・4・5・6月実施 |
全問新作の予想問題でプレ本試験を体験! 【受講料例】 全国模試3回セット 会場受験¥24,200
・全国模試3回セット→全国公開模試 第1回・第2回・第3回 ・全国実力Check模試→全国実力Check模試 ・全国公開模試 各回→全国公開模試 第1回 or 第2回 or 第3回 |
|---|
|
2024年4月~開講 |
本試験傾向・本試験レベルの問題を出題。さらに問われる可能性の高い未出問題にも対応! 【受講料例】 ビデオブース通信講座(会場受験・解説講義あり) ¥82,500 |
|---|
|
2024年合格目標 |
「簡裁訴訟代理等能力認定考査」 対策を万全にする! 司法書士特別研修及び認定考査に対応した講義を実施。認定考査に自信をもって臨むために受講をお勧めいたします。 |
|---|
|
2018年11月実施 |
「簡裁訴訟代理等能力認定考査」 対策を万全にする! Wセミナーが開講する『認定考査対策講座』、『過去問解説講座』、『最新過去問解説講座』、『模擬試験』で構成される特別プログラムを受講することにより、自信をもって認定考査に臨むことができます。 |
|---|
山本オートマチック(2025年合格目標)
|
2024年1月5日申込受付開始
2024年2月~開講 |
年明けからの学習開始で、効率良く自然に合格を目指す! ★【2024年1月5日~】早割キャンペーン実施! |
|---|
|
2023年8月~開講 |
法律用語に苦手意識を感じている方、覚えることが苦手な方にオススメ! 山本浩司講師の卓越した合格理論「オートマチックシステム」で着実に、確実に合格を目指せるコース。法律を初めて学ぶ方、ゆったりしたペースで学習したい方に最適です。 |
|---|
入門総合本科生(2025年合格目標)
|
2024年1月5日申込受付開始
2024年1月~開講 |
長期間で学習でき、確実性を重視する方にオススメの総合コース! ★【2024年1月5日~】早割キャンペーン実施! |
|---|
|
2023年8月~開講 |
3段階学習で、着実にステップアップできる総合コース! 【基礎論点】→【基礎+応用論点】→【アウトプット+知識の整理】の3 段階学習で、森(全体像)→木(各論)を意識しながら、じっくりと知識を定着・ステップアップできます。 |
|---|
山本オートマチック(2024年合格目標)
|
給付制度
2023年9月~開講 |
山本オートマチックの超短期コースで合格を狙う! 山本浩司講師の卓越した合格理論「オートマチックシステム」で短期間で合格を目指せるコースです。 |
|---|
入門総合本科生(2024年合格目標)
|
2023年3月~開講 |
3段階学習で確実性の高い総合コース! 【基礎論点】→【基礎+応用論点】→【アウトプット+知識の整理】の3 段階学習で、森(全体像)→木(各論)を意識しながら、じっくりと知識を定着・ステップアップできます。 |
|---|
本科生(2024年合格目標)
|
給付制度
2023年11月~2024年1月開講 |
【択一式が基準点付近の方向けの本科生】 ・記述式対策講座(26回) |
|---|
|
給付制度
2023年8月~11月開講 |
合格に必要なすべてを提供する総合コース! ・択一式対策講座【理論編】(66回) |
|---|
|
2023年8月~11月開講 |
<山本オートマチック>中上級者向けの総合コース! ・山本プレミアム中上級講座(58回) |
|---|
|
給付制度
2023年11月~開講 |
時期に応じて答練に求められる全てを提供!法改正対策講座で改正点の知識整理もできる! ・総合力底上げ答練(6回) |
|---|
|
2023年11月~開講 |
答練を中心に学習を進めたい!記述式対策を完璧にしたい!その両方を一気に実現できる! ・総合力底上げ答練(6回) |
|---|
パック(2024年合格目標)
|
2024年1月~開講 |
コンパクトなカリキュラムでありながらインプットとアウトプットトレーニングの両立を実現! ・択一式対策講座【実践編】(33回) |
|---|
|
2024年1月~開講 |
年始から全科目で本試験出題可能性が高い論点を”全潰し“し、 直前期は本試験レベルの問題で“合格力完成”へ昇りつめる! ・科目別全潰し答練(12回) |
|---|
|
2023年11月~開講 |
上級総合本科生等の方が答練を追加したい場合に最適! ・総合力底上げ答練(6回) |
|---|
単科生・オプション講座(2024年合格目標)
|
様々なアプローチで【択一式】を基礎から応用まで徹底的に学習!
・択一式対策講座【理論編】 (2023年8月~開講) |
|
様々なアプローチで【記述式】を基礎から応用まで徹底的に学習!
・<山本>オートマチックシステム記述式講座 (2023年9月~開講) |
|
基礎から本試験レベルまで時期に応じた問題演習で実戦力を強化!
・総合力底上げ答練 (2023年11月~開講) |
直前対策コース(2024年合格目標)
|
2024年2月~開講 |
知識があっても点が取れなければ意味がない!過去問を題材に「解法テクニック」を伝授! 山本浩司講師の卓越した合格理論「オートマチックシステム」の直前対策コース。出題者の意図や取捨選択の判断など、合格のために必要な「戦略」を過去問を題材に伝授します! |
|---|
|
予想論点セット 2024年4月~開講 |
本試験で出題可能性の高い論点を直前期に総整理! 「択一予想論点マスター講座」と「予想論点ファイナルチェック」がセットになったお得なセットコースです。本試験の出題傾向の分析に基づき、出題可能性の高い重要論点に絞って取り上げており、本試験予想を十二分に含んでいます。 |
|---|
|
2024年2月~開講 |
法改正(2024年司法書士試験で新たに出題範囲に加わるもの)をコンパクトに押さえる! 2024年の司法書士試験で新たに出題範囲となる法改正(令和6年4月1日時点で施行されている法令)をコンパクトな講義回数で、正確に押さえることを目的とした講座です。 |
|---|
|
2024年2月~開講 |
姫野講師の解法をフルサイズ記述式過去問で実践! 姫野講師の記述式解法で記述式過去問をどのように解くのか。正しい解法の手順を姫野講師自身が解説します。姫野講師の解法をより確実に身に 着けたい方におすすめです。 |
|---|
|
2024年3月~開講 |
本試験形式の記述式予想問題を徹底演習!即効性かつ汎用性の高い解法を習得! 本講座では、本試験形式の記述式問題の演習をしていただき、解法の解説講義で、本試験で実戦的に活用できる解法を習得することができます。 |
|---|
|
2024年2月~開講 |
午後の部は時間との勝負!択一式を1時間以内で解き切るためのノウハウがここに! 午後の部は択一式の解答にかかる時間を抑え、できるだけ多くの時間を記述式に充てることが合格のポイントになります。本講座では午後の択一式をいかに速く正確に解くかに重点を置き、速解のノウハウを余すところなくお伝えします。 |
|---|
|
2024年2月~開講 |
毎年的中多数の「本試験予想論点集」を用いた解説講座! 本講座では「無敵の司法書士 2024年 本試験予想論点表」の中から特に出題可能性が高い論点を姫野講師がピックアップし解説を行います。併せて本書の効果的な使用法の解説も行います。 |
|---|
|
2024年2月~開講 |
人気の受講生限定レジュメを自主リメイクして一般販売!オートマテキスト学習者の学習効率向上に役立ちます! 2024年目標初学者向け山本オートマチックで新たに登場し、たちまち人気を集めた受講生限定レジュメ「厳選 講義の急所」を使いやすくまとめました。受講生だけでなく、全てのオートマテキスト学習者の学習効率を上げる役立ちツールです。 |
|---|
|
2024年2月~開講 |
民訴等を6時間でまるっと総ざらい!短時間で総復習ができる便利講座! 苦手とする受験生が多い民訴等(民事訴訟法・民事執行法・民事保全法)のポイントを6時間で総ざらいする講座です。民訴等に苦手意識のある方や、短時間での総復習を行いたい方におすすめの講座です。 |
|---|
答練コース(2024年合格目標)
|
2024年3・4月~開講 |
直前期の総仕上げに最適!ズバリ的中・論点的中続出の予想問題をギュッと詰め込んだ内容で本試験レベルの実践力を磨き上げる! 本試験レベルかつ本試験予想問題をふんだんに盛り込んだ合格力完成答練と全国模試シリーズがセットになった直前期のお得なコース。本試験予想問題中心の内容ですので直前期の総仕上げに最適です。 |
|---|
|
2024年3・4月実施 |
直前期までの総括&直前期の指針に! 本試験と同じ出題数・同じ試験問題となる総合問題です。本試験の出題傾向を予測した上で科目別全潰し答練・合格力完成答練の総合問題として出題します。 |
|---|
|
2024年4月~開講 |
本試験傾向・本試験レベルの問題を出題。さらに問われる可能性の高い未出問題にも対応! 本試験傾向を徹底分析した本試験レベルの問題を出題します。直前期のシミュレーションに最適です。 |
|---|
|
2024年5・6月実施 |
最新の本試験傾向に対応した全問新作問題!真の本試験レベルの模試! 本試験と同形式で全国規模にて実施!「質」にこだわり抜いた全問新作の予想問題を本番さながらの緊張感の中で解き、プレ本試験を体験できます! |
|---|
|
2024年合格目標 |
「簡裁訴訟代理等能力認定考査」 対策を万全にする! 司法書士特別研修及び認定考査に対応した講義を実施。認定考査に自信をもって臨むために受講をお勧めいたします。 |
|---|
|
2018年11月実施 |
「簡裁訴訟代理等能力認定考査」 対策を万全にする! Wセミナーが開講する『認定考査対策講座』、『過去問解説講座』、『最新過去問解説講座』、『模擬試験』で構成される特別プログラムを受講することにより、自信をもって認定考査に臨むことができます。 |
|---|
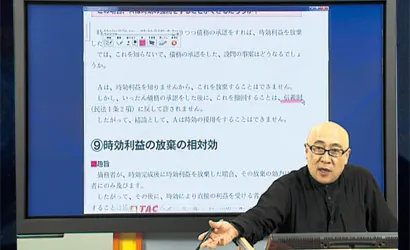
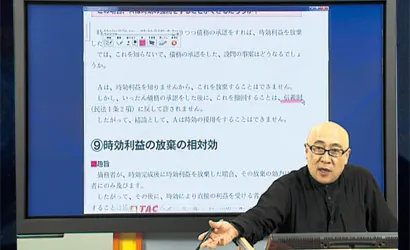
アンケート回答で入会金免除券GET!
【無料】オンラインセミナー・体験講義
司法書士の資格情報や合格するための学習法の紹介、また実際の講義を無料で配信しております。 また「山本オートマチック」「入門総合本科生」どちらのコースにしようか?など、コース選択で迷ってしまった場合も、動画を見て各担当講師と合うかどうか確認することもできます。


合格できるスクールを選ぶなら、
答えはWセミナーです!
Wセミナーは過去問や最新傾向を徹底的に分析し、受験生をより早く合格へと導く様々なコースをご提供しています。これからもWセミナーは、皆様の合格を強力にバックアップします!

デジタルパンフレットを閲覧する
資格の最新情報やTACのコースを掲載したパンフレットを、お使いのデバイスでいますぐご覧いただけます。
お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
Wセミナー 司法書士講座の6大特徴
-

多様な合格法を持つ合格請負人が集結!
実力派講師陣
Wセミナーでは、広範囲にわたる学習範囲を効率的に学習していくために、合格に必要な「講義」「教材」「カリキュラム」を講師自らが立案・作成しています。試験傾向を熟知した講師が提案する合格コンテンツだからこそ、安心して学習に集中でき、合格を実現することができます。
-
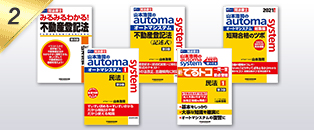
これだけあれば大丈夫!
安心と信頼の教材
市販書籍市場で鍛え抜かれた「山本オートマチック」の教材、徹底した本試験分析で高い網羅率を誇る「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材、毎年多数の的中を誇る答練・模試、それだけで合格が目指せます!
-

講師の多様な個性・合格法と連動!
進化を続ける戦略的カリキュラム
Wセミナーは講師の個性を最大限発揮するため、多様なカリキュラム・コースをご用意しております。講師の思いのつまったオリジナルカリキュラム、学習経験に合わせた多彩なコース設定と、司法書士試験合格を目指す全ての方にぴったりコースが見つかります!
-

ライフスタイルに合わせて選べる!
選べる豊富な学習メディア
講師から直接講義を受けられる「教室講座」、ご自身のスケジュールに合わせて通学できる「ビデオブース講座」、ご自宅で好きな時間に学習できる「通信メディア」と豊富な学習メディアであなたのスタイルに合わせた学習が可能です。
-

欠席フォローも質問も安心!
充実したフォロー制度・学習環境
スムーズに受講を続けられるようお手伝いする「オンラインフォロー」、欠席・復習時に使える「Webフォロー・音声DLフォロー」、学習上の疑問を解消する「質問メール」など、忙しい社会人も安心の充実したフォロー制度を完備しています。


「司法書士」活躍のフィールド
司法書士は不動産登記や商業登記などの登記業務のスペシャリストでありながら、現在士は従来の登記業務にとどまらず、身近な総合法律アドバイザーとして活躍の場を拡げています。司法改革の一環として行われた2002年司法書士法の改正により、司法書士法人の設立が可能になったこと、そして簡易裁判所における訴訟代理権が与えられたことにより、司法書士の新しい可能性が大きく拡がりました。また、成年後見制度に大きく関与するなど、司法書士は市民の身近な法律家として社会の中で重要な役割を担っています。
-
新着情報・キャンペーン情報
-
割引制度