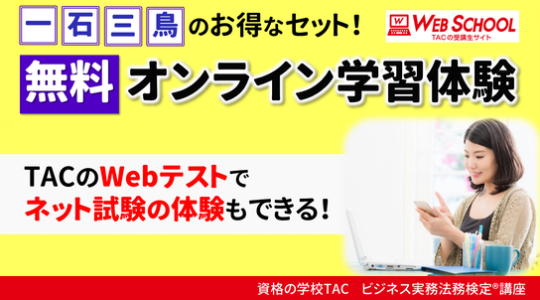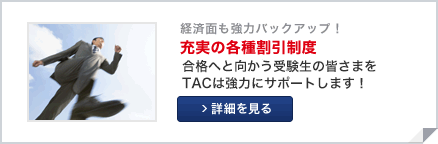ビジネス実務法務検定試験®
ビジネスに不可欠なコンプライアンス・法令遵守能力の基礎となる実践的な法律知識を体系的かつ効率的に身につけることを目的とした試験です。
思い立ったら学習開始!
開講時期や学習レベルに合わせて最適なコースが選択できます!
-
3級、3・2級(初学者レベル)
-
2級(3級修了レベル)
-
1級(2級修了レベル)
開講コース一覧
第1シーズン(6~7月)合格目標
| 給付制度
2024年3月~開講 |
一気に合格を目指そう! 同一試験シーズンに一気に3・2級合格を狙うコースです。TACの短期合格理念をそそいだ効率的カリキュラムで一気に3級と2級の同時合格を狙います。 |
|---|
| 給付制度
2024年3月~開講 |
着実に学習しよう! 同一年内に、第1シーズン(6~7月)検定で3級を、その後、第2シーズン(10~11月)検定で2級と順を追って、着実に合格を目指すコースです。受講のスケジュールに余裕があり、お仕事しながらでも続けやすいカリキュラムです。 |
|---|
|
2024年3月~開講 |
法律と実務のつながりを学ぼう! 法律初学者はここからスタートです。基本を着実にマスターすることにより、知識の広がりが見えてきます。基礎知識をしっかり身につけ、合格を狙います。 |
|---|
|
2024年4月~開講 |
2024年度版 一問一答エクスプレス問題集(TAC出版)使用! 「2024年度版一問一答エクスプレス」(TAC出版2024年2月下旬刊行予定)問題集の中から、今年度出題される可能性の高い問題を中心に取り上げ、解説講義を行っていきます。問題集を使用して独学をされていた方や、最後の総仕上げに利用したい方にピッタリです!! |
|---|
|
2024年5月実施 |
2級本試験の最後の総仕上げ! 2級本試験の最後の総仕上げとして、また最後の予想問題演習の場となる公開模試です。 |
|---|
第1シーズン(6~7月)合格目標
| 給付制度
2024年3月~開講 |
3級合格者にオススメ! 2級合格本科生のカリキュラムに加え、3級基本テキストを使用して復習する2級アプローチ講義(全4回)つき!!3級を独学合格された方にオススメです! |
|---|
|
2024年4月~開講 |
さらなるキャリアアップを目指そう! 3級の知識をベースにレベルアップを狙います。3級の基礎知識をより実践的な知識に引き上げ、さらなるキャリアアップを目指します。 |
|---|
|
2024年4月~開講 |
実戦力を身につけよう! すでに2級の学習を一通りされていて、アウトプットトレーニングのみ行いたい方におすすめのパックです。本試験出題予想問題を含め、多様な問題を解きましょう。 |
|---|
|
2024年4月~開講 |
2024年度版 一問一答エクスプレス問題集(TAC出版)使用! 「2024年度版一問一答エクスプレス」(TAC出版2024年2月下旬刊行予定)問題集の中から、今年度出題される可能性の高い問題を中心に取り上げ、解説講義を行っていきます。問題集を使用して独学をされていた方や、最後の総仕上げに利用したい方にピッタリです!! |
|---|
|
2024年5月実施 |
2級本試験の最後の総仕上げ! 2級本試験の最後の総仕上げとして、また最後の予想問題演習の場となる公開模試です。 |
|---|
2024年12月合格目標
|
2024年3月~開講 |
法律実務のスペシャリストへ! 1級の試験は難易度が高く、試験範囲も広いですが、出題可能性の高い重要分野にポイントを絞った講義で合格を目指します。 |
|---|
|
2024年6月~ |
実戦力を身につけよう! 答案練習を繰り返すことで、身につけた知識を横断的に整理することができます。独学者の方や学習経験者など、一通りの学習をされた方におすすめです。 |
|---|
|
2024年11月実施 |
1級本試験の最後の総仕上げ! 1級本試験の最後の総仕上げとして、また最後の予想問題演習の場となる公開模試です。本試験と同じ制限時間、論文形式で出題します。 |
|---|

【無料】動画で見る!
講座説明会/セミナー/体験講義
ビジネス実務法務検定試験®について、動画でご紹介します!
資格情報や合格するための学習法の紹介、また実際の講義を無料で配信しております。有益な情報が満載ですので、ぜひ動画を見て合格に一歩近づきましょう。

【合格実績・合格者の声】
TACをお選びいただいた方を
短期合格へと導きます!
最少の努力で最大の効果を発揮するTACの講義・答案練習等により、今まで多くの合格者を輩出しています。合格した方の喜びの声もご紹介します。

デジタルパンフレットを閲覧する
資格の最新情報やTACのコースを掲載したパンフレットを、お使いのデバイスでいますぐご覧いただけます。
お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
ビジネス実務法務検定試験®講座の6大特徴
-


受験指導経験豊富!
頼れる講師陣
短期合格のためには、講師の指導が重要なポイントとなります。TACでは、ただ単に知識を提供するだけではなく、理解して覚えるための講義を行います。合格はもちろん、実務でも活かせる知識が養える熱い講義を目指しています。
-


出題範囲が広くても安心!
効率的カリキュラム
長年の受験指導で培ったノウハウを注ぎ込んだTACのオリジナルカリキュラムには短期合格の工夫が盛り込まれています。「合格するための最小限の講義時間」を常に意識したTACのカリキュラムはムリ・ムダのない「短期合格の秘訣」となります。
-


重要ポイントを押さえられる!
オリジナル教材
TACでは合格に直結した『TACオリジナルテキスト』を使用します。テキストは試験傾向にあわせて毎年改訂を行っています。合格に必要な知識をスッキリと整理できるよう工夫を凝らしたテキストで、一気に合格を目指してください。

企業が求める、ビジネスシーンで
必要とされる実践的な法律知識を
身につけられる!
企業において不祥事の発生は、刑事責任や損害賠償などの民事責任を負うほか、社会的信用を失い、事業継続が不可能となる事態を生じかねない大きな問題です。企業が継続的な企業活動を行っていくためには、従業員一人ひとりがコンプライアンス(法令遵守)能力を身につけ、リスクを事前に認識し、回避・解決できることが求められます。そのため、近年では社内の推奨検定としたり、人事異動や採用時の参考資料として取り入れる企業も増えています。